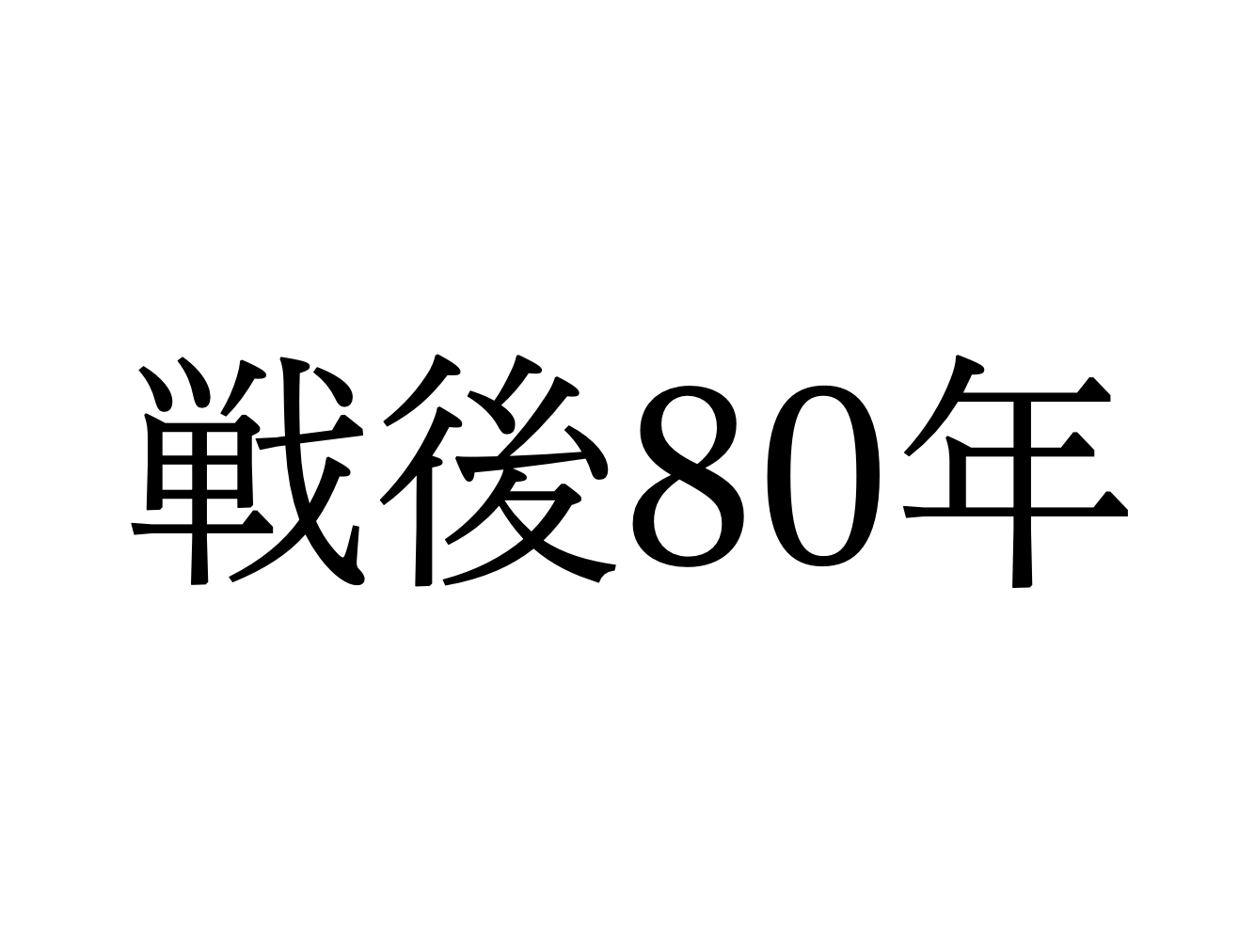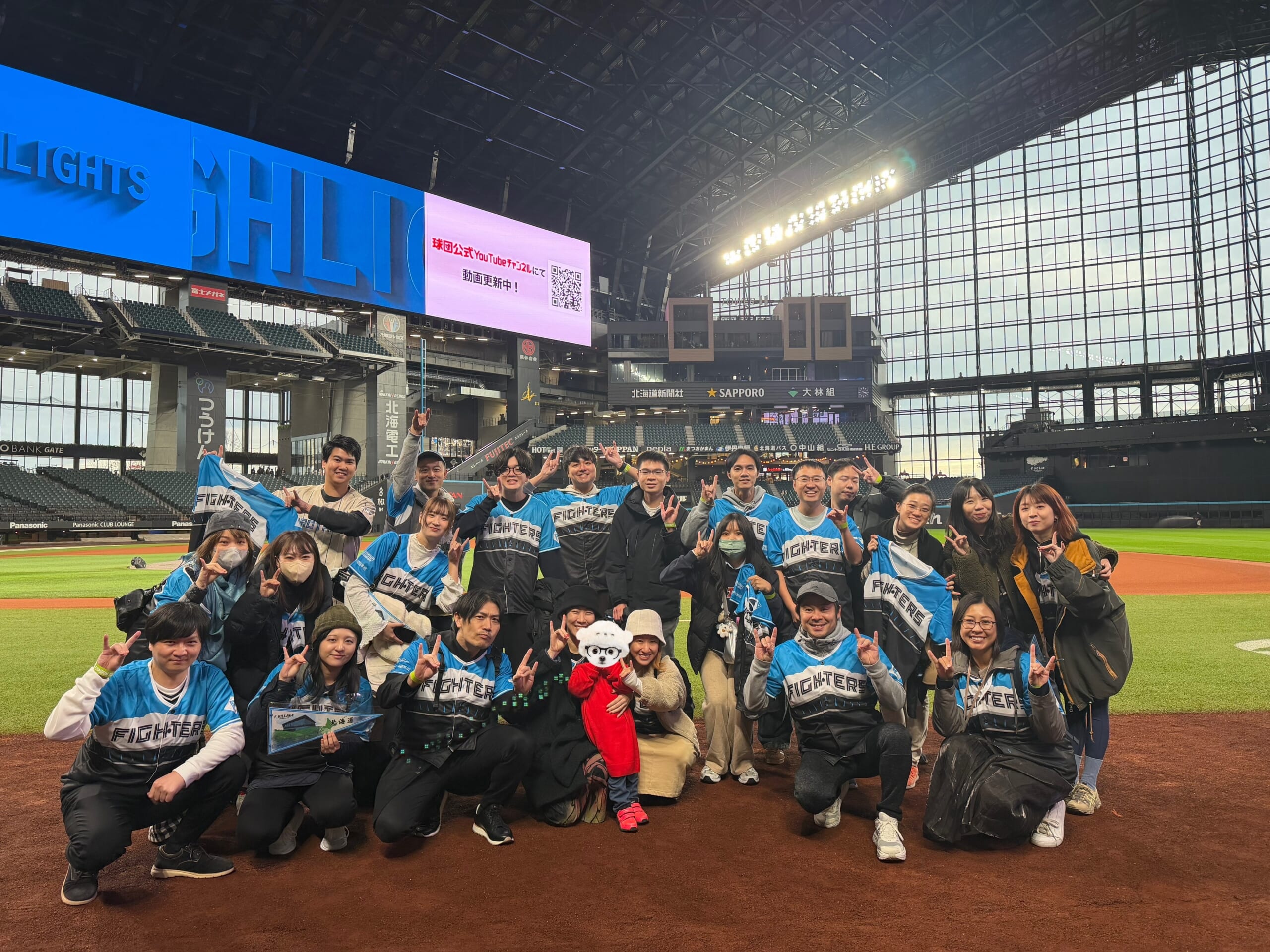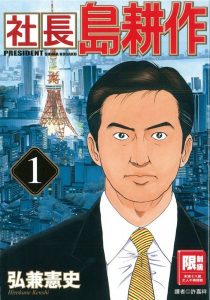八月、正午。サイレンと蝉時雨
八月の熱、正午のサイレン。
三百万人を超える死者、焼け落ちた街、飢えと病に苦しむ人びと。
私たちは長く「軍部の暴走」という物語で戦争を語ってきたが、それだけでは全体を説明できない。
破局を招いたのは、国家の制度と文化、そして私たち自身の判断の癖でもあった。
その癖は形を変え、いまの社会や企業にも残っている。八十年の節目に、過去を振り返る。
黒船という外圧——突きつけられた「近代化か、植民地化か」
1853年、浦賀に黒船が現れ、日本は否応なく国際秩序に引き出された。
帝国主義の最盛期、アジア各地は植民地化され、不平等条約が常態だった。
治外法権、関税自主権の欠如——主権が侵食される現実の前で、日本が近代化を選ぶことは避けがたかった。
富国強兵、殖産興業、教育制度の整備、軍備の近代化。これらは、飲み込まれないための最低条件だった。
日清・日露——勝利が「常識」を作り替えた
日清戦争の勝利は賠償と領土をもたらしたが、三国干渉の屈辱も刻んだ。
「次は退かない」という世論が生まれ、日露戦争の勝利でそれは確信に変わる。
講和条件が期待に届かず不満は残ったが、国家に定着したのは
「軍事的拡張は国益、戦争は外交の延長」という新しい常識だった。
国防のための軍備は、いつしか影響圏拡大を前提とする軍備へ。
勝利は自信を育てたが、同時に「次も同じやり方でいける」という思い込みも育てた。
総力戦の方程式——資源と生産力が勝敗を決める
第一次世界大戦は、戦争を根底から変えた。戦いは戦場の兵士だけでなく、国家の総力が左右する。
石油、鉄、ゴム、銅、ボーキサイト——資源と生産力、そして兵站がすべてを決める。
この戦争は日本にとって対岸の火事で、好景気と領土獲得に沸いた。
しかし若い指導層は危機を見た。次はさらに厳しい総力戦になる。 欧米はアジアの権益に深く踏み込み、衝突の余地は広がる。
そのとき日本はいかに自国を守るのか。資源に乏しい国土から見れば、満州や南方は「自活の動脈」に映った。
当時の為政者には合理的に見えただろう。だが資源の元締めは米英であり、そこに手を伸ばせば摩擦は避けにくい。
局地的には筋が通っても、全体としては正面衝突へ向かう一本道だった。
調整役を失い、軸が揺れた——制度の欠陥が意思決定を壊す
明治から昭和初期まで、日本には最終調整役の「元老」がいた。
彼らが退くと、国家の意思決定は陸軍と海軍の力学に左右されるようになった。
陸軍は大陸重視、海軍は南進重視。
止める役がいなくなり、政策の軸が失われた。
さらに、統帥と内閣の権限が二重構造のまま残り、政治が軍を統制し切れない設計が温存された。
「どちらも否定しない」ことが無難とされ、「両案を抱えたまま前進する」事なかれが常態化。
判断は先送りされるのに、情勢だけが先に進み、撤退コストが膨らんでいく。
始め方は語られ、終わらせ方は用意されなかった——出口戦略の不在
資源確保という開戦理由は、文書上は整っていた。
しかし、終戦の設計図は用意されていない。
「短期で優勢に立てる」「相手は和平に応じる」「第三国が仲介するはずだ」——都合の良い前提が、欠けている現実を塗りつぶした。
兵站・海上輸送・補給線防衛といった地味で難しい論点は、精神論や空気の勢いに押しやられた。
結果として日本は、「始められる戦争」を選び、「終われない戦争」を背負った。
支持と沈黙が、誤った進路を後押しした——世論の責任
戦後の語りは「軍部の暴走」に収れんしがちだ。もちろん軍の責任は重い。
だが、新聞が戦意を煽り、演説に拍手が起こり、出征兵士が旗に囲まれて見送られたのも事実だ。
支持と沈黙が、誤った進路を後押しした。
情報統制があった一方で、異論を言いづらい雰囲気も社会を覆っていた。
「疑問を口にすることが場違い」とされる空気が、判断の幅を狭めた。
この構図を直視しなければ、同じ歯車は何度でも回る。
ラベルではなく、結果で向き合う——慰霊と責任の線引き
中国や韓国には、靖国神社にA級戦犯が合祀されていることを問題視する声が多い。
ただしA級・B級・C級という分類は、戦勝国が付したラベルに過ぎない。
私たちが向き合うべきは、三百万人以上の死という結果だ。
靖国神社は戊辰戦争以降、日本のために命を落とした軍人・軍属を、階級や地位に関係なく慰霊するという理念を掲げる。合祀は宗教上の行為であり、政治判断ではない。
ただ、おびただしい数の犠牲者を生んだ当時の指導層について、私は名もなき犠牲者と同じ形で顕彰することには慎重であるべきだと考える。
あの戦争を止められず、国土を焼かれ、二発の原爆を受け、無数の悲劇を生んだ責任は、計り知れない。
敗因は、いまも会議室に座っている——五つの病理
当時の敗因は、次の五つに要約できる。どれも、いまの会議室に見覚えがあるはずだ。
- 事なかれ主義——衝突を避け、決断を先送り
反対意見を出すと「空気が悪くなる」と敬遠され、重要論点が棚上げになる。
先送りはリスクを利息付きで増やすが、その利息は見えにくい。 - 官僚体質——縦割りで全体最適が消える
部門の最適化が積み上がっても、全体の最適にはならない。
「所掌外」が口癖になると、誰も全体の責任を取らない。 - 精神主義——不足を根性で補おうとする
士気は重要だが、現実の不足は埋められない。
現場の献身が、構造問題を覆い隠す副作用を持つ。 - 希望的観測——都合の良い未来だけを見る
最良シナリオだけを採用し、最悪シナリオを具体化しない。
「できるはずだ」が、いつの間にか「できている」に置き換わる。 - 情報軽視——データより“空気”を信じる
指標より経験則、検証より前例。
測らないものは、必ず見誤る。
不祥事という鏡——現代に現れた同じ顔
五つの病理は、時代と看板を変えて今に現れる。
- 東芝の粉飾
見た目の安定を優先し、問題は先送りされた。
報告や会議体は形を保ったが、実質の点検は機能不全に陥っていた。 - 神戸製鋼のデータ改ざん
長年の慣行が現場を縛り、縦割りが視界を狭めた。
誰も「全体の品質」を引き受けないとき、不正はいつの間にか“作業”に変質する。 - 三菱自動車の燃費不正
技術と時間の不足を、方法のごまかしと場当たりの努力で埋めようとした。
精神主義は一時の檄にはなるが、構造は変わらない。 - スルガ銀行の不正融資
高い目標を前に、現実のほうをねじ曲げた。
「できるはずだ」という見込みが、数字や手続きの線引きを溶かす。 - 日産の完成検査不正
「こうしてきた」という慣行が、規程より強くなった。
手続きが目的化し、品質は儀式に落ちたとき、はじめて欠落に気づく。
いずれも個人の倫理だけに帰せない。設計と文化が、人を誤りへ押し出す。
世界は何処へ向かうのか——とまらぬ再軍備の流れ
世界的な軍拡が止まらない。米国は2026年度に防衛費1兆ドル(約143兆円)規模を計画し、EUは8千億ユーロ(約132兆円)の再軍備投資で域内調達比率を60%へ引き上げる。
日本も防衛費をGDP比2%へ段階的に引き上げ、装備調達を多角化。中国や中東の軍拡も進み、AI・無人機など新技術の導入競争が激化している。
なかでも東アジアは世界屈指の緊張地帯だ。航空自衛隊のスクランブルは2013年度以降、年間700回超が常態化する高水準が続く。
「米国の傘」に全面依存して平和を謳歌できる時代は、以前より格段に不確実だ。
もう一度国土を焦土にしないために、憲法の議論を含め、自国を自分で守る責任を正面から考え直すときに来ている。
再発を防ぐための実務——五つの手順
反省を手順に落とす。ここからしか、再発防止は始まらない。
- 対立を設計する
重要案件には反対役(レッドチーム)を置き、異論提出を義務化。論点と反証を文書化する。 - 全体最適の責任者を明示する
部門横断の「最終停止権」を制度化し、「止めた責任」を評価する。 - 数字で語り、例外を記録する
目標・現状・ギャップを定量化し、前提条件を明記。例外運用は台帳で追跡し、期限を区切って是正。 - 最悪の台本(プレモータム)を先に書く
失敗が起きた前提で、原因・兆候・対処を合意しておく。「起きないはず」を前提にしない。 - 空気の可視化
会議前に匿名で懸念・反対を集計し、分布を共有。見えない圧力を数字で扱う。
結び——八十年目のハンドルを握り直す
戦争は過去の棚にしまわれた本ではない。
会議室の沈黙、前例踏襲、楽観的で心地よい見通し、異論を言いづらい雰囲気——それらが積み上がる先に、あの光景がある。
「軍部が悪かった」で終わらせれば、同じ構造は形を変えて戻ってくる。
だから、私たちは引き受けなければならない。
間違えたのは国家であり、同時に私たちだと。
その認識から、次の一歩が始まる。
八十年目の夏、サイレンが止む前に——もう一度、ハンドルを握り直そう。