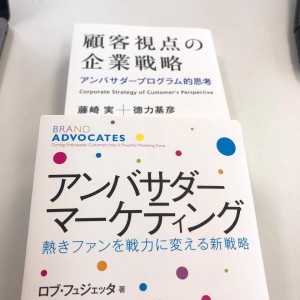台湾で人気No.1のラーメン店、待望の台湾出店
かねてより、アツい台湾ラーメンファンたちの注目を一身に集めていた一蘭ラーメン台湾出店の日取りが、6月15日に決まったそうです。
一蘭ラーメンの台湾出店が発表された時はそれはもう各メディア大騒ぎでした。
社長のコメントが主要メディアを駆け巡ります。
「台湾出店が決まって嬉しい!」と口々にコメントする、街の人々。
「台湾での知名度が最も高いラーメン屋です」
「これでもう日本に行かなくても食べられる」
などなど、歓迎する声多数でした。
しかしながら「日本に行かなくても食べられる」というのは、言い方を変えれば「いつでも食べられる」更に言えば「特別感がなくなり、非日常ではなくなる」ということです。
「非日常をSNSで共有したい」というユーザ動機の喪失
近年の一蘭ラーメンの台湾における人気の一端を担ってきたのは、間違いなくSNSです。SNS解析で実績の多いナイトレイによる調査では、2016年のグルメスポットに関する投稿では、一蘭の投稿が2番目に多かったとレポートされています。
日本と比べ、台湾はテレビや新聞のメディアパワーが極めて小さい一方で、Facebookのアカウント保有率は全人口の65%以上にのぼります。ゆえに台湾マーケティングでは、SNS(=FacebookとInstagram)での訴求が非常に重要な鍵を握ります。SNSが大好きな台湾人は「いま一蘭のラーメンを食べてます!」とFacebookやInstagramに投稿する事で「日本に来ています!」という旅行の特別感や非日常感を友達とシェアしてきました。しかしながら、日常的に食べられるようになれば、特にいいね!(中国語で言うと「讚!」)を集めるようなものではなくなってしまう、ソーシャル上の訴求力を喪失すると言うことです。
「限定」の魔力
我々日本人もそうですが、台湾人は我々以上に「限定」の二文字に弱い傾向があります。「期間限定」「日本限定」と言われると、ついつい買ってしまうのです。
例えば、当社「ラーチーゴー!日本」では、よくコンビニ特集を行うのですが、コンビニでダントツのアクセスを集めるのは、ローソンとセイコーマートです。理由は簡単で「台湾に無いから」(セブンイレブンとファミリーマートは台湾中のいたるところにあります)。

↑ローソン

↑セコマ
「限定」の二文字が生み出す飢餓感や枯渇感が大きく減少する事はまちがいありません。
熱しやすく冷めやすい人たち
ふだん台湾にいて思うのは、「日本からの出店はだいたい大人気になる、そしてすぐ飽きられる」という事です。
ある程度日本で名の知れた飲食店であれば、台湾進出が決まるとメディアは騒ぎますし、オープンと同時に店前には長蛇の列ができます。しかしその人気が長続きする事は極めて少ないです。去年〜今年で相当数の飲食店が台湾に出店し、その大半が開店と同時に大人気を博し、数ヶ月先まで予約がいっぱいという状態でしたが、今はほぼいつでも予約なしで入れる、あるいはガラガラという状態です。
多くの台湾人が待ち望んだ一蘭の台湾出店ですが、それにより非日常の特別な存在であったものが、日常にありふれた存在になります。上にリンクを貼った2つ目の動画でグルメブロガーのおっさんが言っているように、台湾における日本ラーメンブームもぼちぼち終わりかも知れません。もちろん、一蘭としては当然それを承知の上での長期戦略に基づいた台湾進出だと思いますが、これまでラーメン店としては圧倒的な人気を誇っていただけに、今後「一蘭」というブランドが台湾でどう変遷するか注目です。